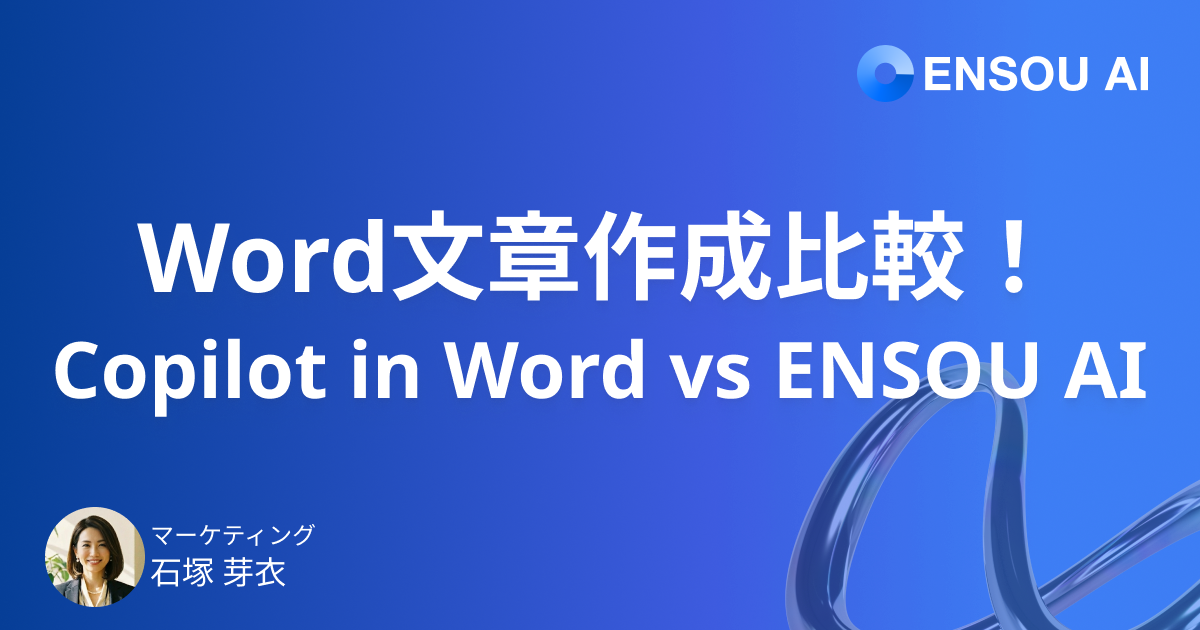2025年11月26日
月500件以上の問い合わせ対応を自動化、社員の500名が利用。さくらケーシーエスがENSOUチャットボットで属人化解消と業務効率化を実現
— 500件以上の社内問い合わせ対応の自動化と属人化解消を実現。神戸発の大手システム開発企業と神戸発のAIスタートアップによる協業で業務効率化を推進 —


株式会社さくらケーシーエス
常務執行役員 CISO 新見昌弘 様
情報システム部長 名村浩一 様
情報システム部 システム管理グループ長 梅木英幸 様
情報システム部 システム管理グループ マネージャ 寺山傳一郎 様
ENSOU AI導入の背景と取り組みの効果
- 月間500件以上の問い合わせの対応に追われ、本来着手すべき生産的な業務に割けるリソースが減少
- 社内の情報が特定の個人の経験や勘に基づいており、知識が属人化。不在の場合の対応に苦心
- 他の製品を試したものの、想定した用途に合わず導入を断念
- セキュアな環境で社内情報とAIを紐づけるRAG構築の取り組みを容易に実施
- 翻訳業務や書類作成など、生成AI本来の業務効率化の動きも拡大
- 月間500件以上の問い合わせ対応を自動化し、手を止める時間や時間外対応を大幅に削減
- 約500名が業務で利用しており、特に新入社員や若手の自己解決を支援する仕組みとして定着
- データ更新→回答精度向上→問い合わせ削減という好循環が生まれ、ベテラン社員の暗黙知を共有財産に
- 業務マニュアルや手順書、社内規定などのFAQデータをベースにしたRAG構築による問い合わせ対応の自動化
- オンボーディング手順を自動回答化
- 翻訳業務、書類作成、エラー調査、コーディングなど一般的な生成AIの業務活用
導入企業概要
株式会社さくらケーシーエス(本社:兵庫県神戸市)は、東証スタンダード市場にも上場しているSMBCグループの総合情報サービス企業です。金融・公共・民間企業向けに、システム企画・開発から運用管理、デジタル基盤構築まで一貫したITソリューションを提供しています。直近では情報システム部が主導して、社内でもAIを活用した業務効率化に向けた取り組みを進めています。
また、さくらケーシーエスは、神戸発のAIスタートアップである株式会社Digeonと協業し、ENSOUチャットボットを通じて「神戸発の先進的なAI活用モデル」を実現しました。
今回は、常務執行役員 CISOの新見様、情報システム部の梅木様、名村様、寺山様の4名に、導入の経緯とENSOUチャットボットによって起きた社内の変化について伺いました。
課題は問い合わせ対応への疲弊と属人化
― まずは、情報システム部の業務内容と、今回のAI導入に至った背景を教えてください。
名村様: 情報システム部では、社内システムの運用を中心に、各システムのリプレイスや新規企画も担当しています。その中で、日々、現場からの問い合わせが非常に多く、担当者が対応に追われていました。これをどうにか改善できないかというのが、直近の課題でした。
新見様: 経営層としても「属人化」は大きな課題でした。担当者が不在の場合、帰ってくるまで回答が得られないというケースも多々ありました。業務への影響を最小限にするためにも、社内データとAIの連携を強化し、誰もが簡単にFAQデータにアクセスできる仕組みが必要でした。
梅木様: 昨年1年間で社内のドキュメント整備が進み、AIで活用できるフェーズになってきたことも大きいですね。ちょうど、チャットボットを本格的に導入できる準備が整ったタイミングでした。

― 生成AIチャットボットの導入を検討されたきっかけは?
新見様: 元々、上記のような課題認識と解決手段の構想はありました。そんな中で、専門的な知識や厳密なデータ成形を必要とせず、より柔軟に社内ドキュメントを活用できる「生成AIチャットボット」が最も現実的だと判断しました。
― ENSOUチャットボットを選んだ理由を教えてください。
新見様: 実は最初、他の大手ベンダーにチャットボット構築を依頼していました。しかしPoCを実施したものの、想定していた業務シナリオで十分に機能せず、社内での実運用には至りませんでした。社内で改善を試みたものの、専門的なAI知識が必要となり、品質を自社で適切に評価することすら難しい状況でした。
そこで「実務を理解した上で、業務に使える精度まで仕上げてくれるパートナーが必要だ」と判断し、AIの専門家であるDigeon社に相談しました。最初はセカンドオピニオンとしてアドバイスをもらっていたのですが、やり取りを通じて“技術的な知見だけでなく、現場に根づくAIの活かし方”を深く理解していると感じ、最終的に導入まで一貫してお願いすることにしました。
今回のプロジェクトで重視したのは、「プロンプトを工夫しなくても、誰でも正確な回答が得られること」でした。ENSOUチャットボットの導入では、エンジニアが実際の業務フローを理解したうえで細部まで調整してくれたことで、単なる技術導入にとどまらず、“現場で自然に使われるAI”を実現できたと感じています。
500件以上の問い合わせの対応を自動化し、オンボーディングにも活用
― 実際にどのような業務で活用されていますか?
梅木様: 社内の問い合わせ対応が中心です。例えば、PCの端末入れ替えやワークフローに載らない申請手順、社内規程などのFAQデータをENSOUチャットボットに連携し、RAGを構築しています。今ではENSOUチャットボットに聞けば、すぐに解決できる環境が整いました。
寺山様: 10月はシステム関連の質問だけで、チャットボットに約200件の質問が寄せられました。これまで全て有人対応だったものが、AIで自動処理されるようになったのは大きいです。結果として時間外対応も明らかに減りました。
新見様: 問い合わせ対応だけでなく、新入社員のオンボーディングにも活用しています。10月に入社したメンバーには、「PCセットアップはENSOUチャットボットに聞いてください」と案内しており、実際に自力で解決できるケースが増えています。

― 導入効果について教えてください。
梅木様: 導入前は1人あたり、社内システム関連の問い合わせだけでも1日10〜20件あり、10人チームで100〜200件/日の対応をしていました。ENSOUチャットボット導入後は、単純な質問の多くが自動化され、手を止める時間が減少しました。スイッチングコストの削減効果は想像以上です。実際に利用している社員からチャットボット内で「ありがとう」と感謝のメッセージが送られることも多々あります(笑)。単なるツールではなく、“社内の頼れる存在”として浸透していると感じます。
寺山様: 公開後、社内の500名ほどがすでに利用しています。特に若手社員は、先輩に直接聞くよりもAIに聞く方が心理的ハードルが低いようで、急速に定着が進んでいる印象です。公開当初は、問い合わせ対応目的の利用がほとんどでしたが、ENSOUチャットボットの使いやすさから、翻訳やエラーコード調査、コーディング、文章作成など、普段の業務でも利用するメンバーが増えています。
新見様: 担当者が繰り返しの質問対応に追われる必要がなくなり、本来実施すべき生産的な業務に集中できる環境になりつつあります。また経営層が重視していた問い合わせ対応の属人化についても、一度データを追加すればAIが自動で回答してくれるので、ナレッジ整備のインセンティブにもつながっています。
データがAIに連携されることで、社内文化が変わりつつある
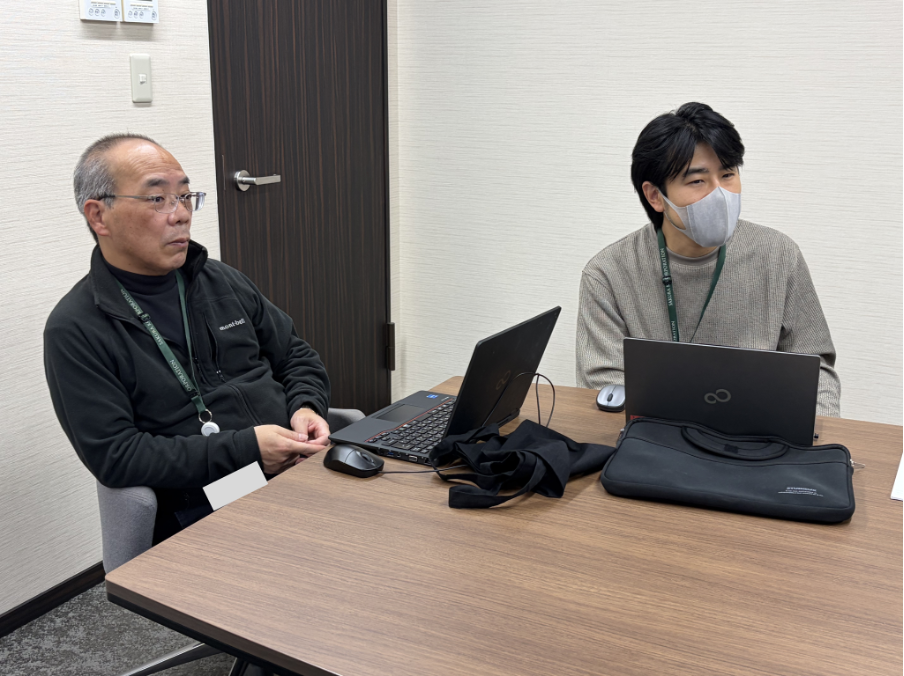
― 現在の運用体制と、今後の展望をお聞かせください。
梅木様: FAQデータのブラッシュアップを月2回のペースで実施しています。AIが答えられなかった質問を蓄積し、“社内広辞苑”のようにナレッジを拡充していく運用を行っています。以前はデータを更新しても見られないために後手になることもありましたが、今ではそれがすぐに回答に反映されるため、細かく更新作業ができるようになりました。
新見様: ENSOUチャットボットの導入で、単なる業務効率化にとどまらず、データの更新→回答の精度向上→問い合わせ対応の減少という好循環が生まれ、社内の情報共有文化そのものが変わり始めています。そうなることで属人的な暗黙知が減り、回答する側、質問する側双方の生産性向上に繋がっています。今後は、AIを活用できる人材を増やしながら、全社的な生産性向上を目指していきます。
さくらケーシーエス様、改めてインタビューへのご協力をありがとうございました。
RAG構築による問い合わせ対応の自動化だけでなく、AIとデータを連携させることで「データを整備したくなる仕組み」が生まれ、結果的に属人的な暗黙知が減少するという好循環のエピソードがとても印象的でした。
ENSOUチャットボットでは、現在フリープランを提供しており、RAG構築を含むすべての機能を気軽にお試しいただけます。
無料ですぐに使えるフリープランのご利用開始はこちらから👇
ご相談、無料トライアルは以下からお問い合わせください👇
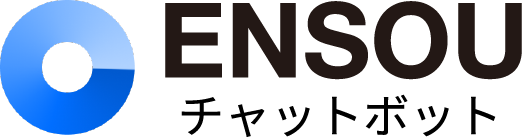

.png)