【社内Wiki】マニュアル管理のベストプラクティス10選【FAQ】
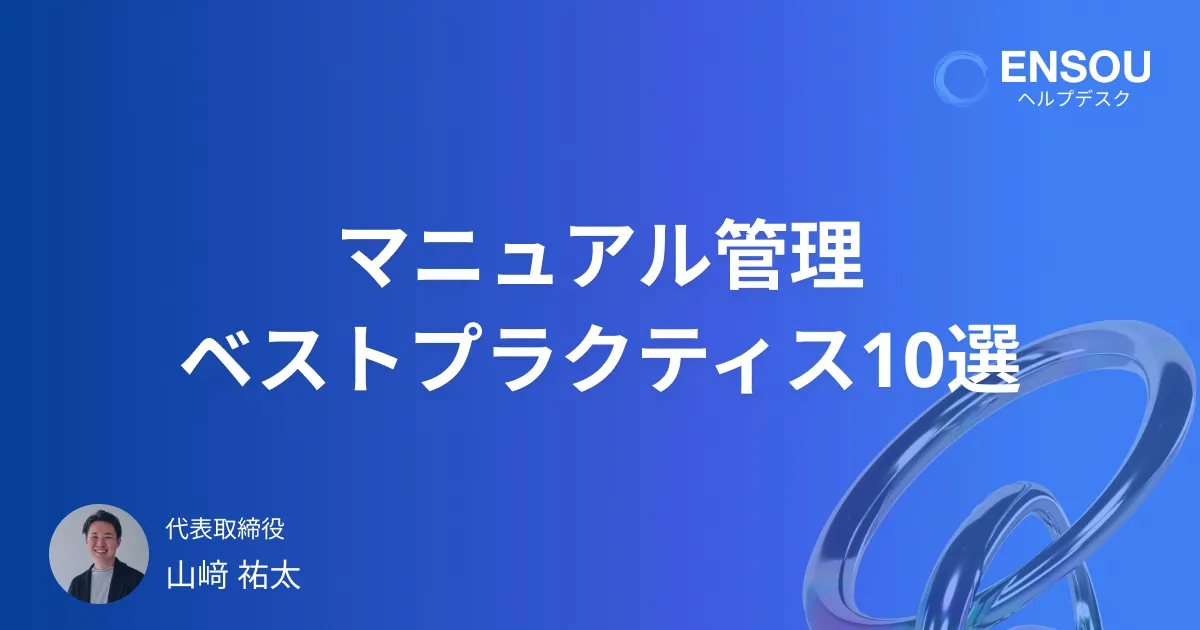
社内Wiki・マニュアル管理のベストプラクティス
社内Wiki・業務マニュアルは、企業が業務を高品質・効率的に遂行するために、また業務の属人性を排除するために必要なドキュメントのひとつです。
一方で適切にマニュアルを運用していくには、
- 社内の全員がアクセスしやすい場所に整理して配置する
- 業務に変更に伴い必要な更新を加えて形骸化しないようにする
- 適切な部署や職位の人のみに閲覧できるよう権限を管理する
- 重複などが発生すると統合や削除など定期的なメンテナンスを行う
といった動きが必要となり、これらを全て実施するのは簡単なことではありません。
本記事でご紹介するベスト プラクティスは、社内Wiki・業務マニュアルを実際の運用環境で役立ち、正確で、アクセスしやすいものにする方法についてご紹介いたします。
これらのベストプラクティスを全て備え、AIエージェントが自律的に業務データからマニュアルを構築するENSOUヘルプデスク👇
1. 文書の目的を明確にする
マニュアルを新規で追加する際には、その目的や意義を明確にする必要があります。
よくある課題としては、過剰にマニュアル化してしまうことで、従業員が適切なマニュアルを探すことに苦労してしまうことや、無関係の記述が多く読む手間が大きくなるなどが挙げられます。
優れたマニュアルを制作するには、現状の業務とマニュアルの課題を明確にし、その課題を解決するためにマニュアルを追加・更新することが重要です。
またそれらがなるべく既存のマニュアルとバッティングせずに、それぞれのマニュアルの役割が明確になる状態を維持しましょう。
2. 責任者をマニュアル毎に明確化する
マニュアルを運用するには、定期的なメンテナンス業務が重要です。
作成当時にどれだけ充実したドキュメントを執筆したとしても、1年後2年後には役に立たないどころか、実際の業務と乖離がある迷惑なドキュメントになる可能性があります。
そのためには、そのドキュメントを運用する責任者・責任を持つ部署・課・チーム・職位などを明確にし、誰が責任を持ってメンテナンスを行うかを明確にする必要があります。
一番は誰が責任を持つか、現在の担当者が変わったときに誰が引き継ぐかを明確にし、時間が経過して異動などがあった後にも、継続的にメンテナンスできる仕組みを作ることが重要となります。
3. 主要業務としてマニュアルを扱う
営業であれば主要業務として、リード獲得方法・アポにおけるトーク・製品紹介資料の更新など、継続的に既存の仕組みを改善していきます。またこれはどの部署や役割においても同じことです。
マニュアルも主要業務のひとつであると考えましょう。
- どの記事が読まれていて、どの記事が読まれていないか
- 文字の大きさ、見出しの使い方、画像の有無が、読みやすく伝わりやすい内容か
- 既存業務との乖離が生じているマニュアルがないか
といったことを日々の業務の中に落とし込むことができれば、継続的に優れたナレッジマネジメントを実現することができます。
そのために、マニュアルの運用も主要業務のひとつであると認識できるよう、社内に働きかけていきましょう。
4. 更新の手間を下げる
ナレッジ管理において重要なのは、前述のとおり継続的に更新を行うことです。
それを実現するためには、更新の手間を下げることが重要です。
基本的にマニュアルの更新作業などは、どうしても前向きに捉えることが難しい業務のひとつです。その中で更新に手間がかかるようであれば、継続的にメンテナンスされた優れたマニュアルを実現することが難しくなります。
コメントの投稿を推奨する、更新提案をしやすいシステムを使用する、編集可能な権限を広めに付与する、変更依頼があればすぐに対応するなど、可能な限り変更へのハードルを下げるようにしましょう。
そのため、細かい文体の違い、面倒なフォーマットなどは多少許容し、積極的に更新をすることが素晴らしいという文化を作りましょう。
5. 自動化する
ドキュメントの更新をしやすい文化を作るのと合わせて、仕組みでマニュアルの編集に気付きやすい状態を作ることも重要です。
- 最終更新から一定期間が経過した記事
- アクセス数が数ヶ月間に渡り0やそれに近い記事
といった傾向は、メールやチャットなどで自動でリマインドされるように設定し、マニュアルを更新するためのきっかけを提供できるようにしましょう。
6. バージョン管理
優れたドキュメントには継続的な更新が重要な一方で、更新がかかるということは過去の変更を適切に管理する機能が必要です。
例えばWordなどでバージョンを管理することもできますが、チームで正確に変更を管理したい場合は、そのような機能を持ったナレッジ管理システムを活用するのが良いでしょう。
特に社内システムの更新に関するもの、人事労務などの法や社内規定の変更に関するもの、法務などリスクが高いドキュメントについては、適切に自動でバージョンを管理しなければなりません。
7. マニュアルの活用を推進する
マニュアルを作成して継続的にメンテナンスできるようになること、そしてそれ以上に重要なのはマニュアルを問い合わせ前に読んでもらうことです。
どれだけ優れたマニュアルでも読まれずにすぐに電話で問い合わせをされてしまっては、意味がありません。
社内ポータルの問い合わせ画面の上部にマニュアルへのリンクを配置してマニュアル参照を促す、入社時の研修で徹底的にマニュアル駆動で動くことを伝える、半年や年間などのマニュアル更新のタイミングで継続的にマニュアルの存在を伝える、といった取り組みを通して、使われるマニュアルを構築していきましょう。
8. データ分析
どんな記事がよく読まれているか、どの記事の評価が高くどの記事の評価が低いのかを分析しましょう。
これによって、従業員の自己解決に貢献している記事、よく見られているが結果的に解決できず問い合わせに繋がっている記事など、記事について定量的・定性的な状況を理解できます。
これらの示唆を得ることで、マニュアルを改善する、そもそも疑問に持たないよう業務やシステムを改善する、といった行動に繋げることができます。
9. 情報をリンクさせる
従業員は常に正解が書かれたマニュアルを参照できる訳ではありません。
例えばパスワード再設定に関する課題があるとしたら、あるシステムのパスワード再設定の記事に、異なるシステムの場合はどのように対処しているのかを記したマニュアルのリンクを貼りましょう。
またナレッジ管理ツールの関連記事や同一カテゴリの他の記事を表示させるのも良いでしょう。
また情報をリンクさせることは、新たな関連知識の獲得にも役立ちます。
ある申請方法について分からない従業員が自身の課題を解決する記事を参照しているときに、関連する異なる申請に関する情報がリンクされていれば、ついでに見ておこうという行動に繋がります。
情報のリンクは、課題解決だけではなく、中長期的な従業員の教育にも役立てることができます。
10. 成果を振り返る
社内Wikiや業務マニュアルの運用は、「作成すること」や「更新すること」が目的ではなく、実際の業務成果に結びついていることが何より重要です。
例えば以下のような具体的な成果とマニュアル運用の関連を明確にすることで、関係者のモチベーションを高め、運用を持続しやすくなります。
- 問い合わせ件数の削減:「このマニュアルを導入した後、月間のチャット・電話問い合わせが20%減少した」など。
- 新人教育の効率化:「マニュアルを活用することで、研修期間を2週間から1週間に短縮できた」など。
- 業務ミスの削減:「チェックリスト型マニュアルの導入後、ヒューマンエラーが半減した」など。
- ナレッジ共有の促進:「部署を超えて他部門の業務理解が進み、属人化の解消が進んだ」など。
これらの成果を定期的に振り返り、チームに共有することで、「マニュアルのメンテナンスは単なる雑務ではなく、組織の成長と成果に直結する重要な活動である」という意識を根づかせることができます。
また、定量的な効果だけでなく、「誰でも迷わず業務を進められるようになった」「教育担当の負荷が減った」といった現場の声も収集し、社内報や全社共有の場で発信することも効果的です。
運用の継続には成果が見える化されていることが何よりのインセンティブです。 そのためにも、社内でのマニュアル活用実績を定期的に評価・報告し、運用の質と価値を高めていきましょう。
ENSOUヘルプデスクで自走するマニュアル運用へ
ENSOUヘルプデスクは、上記 10 項目すべてを網羅するだけでなく、AI が有人対応履歴から自動でマニュアルを生成・更新し続ける次世代ナレッジマネジメントを実現します。
ベストプラクティス | ENSOUヘルプデスクの仕組み |
|---|---|
目的を明確化/責任者割当 | チケット種別・部署タグで自動分類し、オーナーをワークフローで設定 |
知識を“製品”として改善 | 閲覧数・解決率ダッシュボードを標準搭載、AB テストも可能 |
貢献しやすさ | チャット欄から“改善提案”をワンクリック投稿 |
自動化 | 最終更新やアクセス低下を検知し、担当者へリマインド |
バージョン管理 | Git ライクな差分ビューとロールバック |
活用教育 | ボットが検索ヒントを提示、最適記事へ自動ディープリンク |
利用分析 | 問い合わせ件数・一次解決率を KPI 化しレポート配信 |
文脈明示 | 動的テンプレートで対象読者・適用範囲を自動記載 |
成果連動 | ROI レポートで「問い合わせ削減%」「研修短縮日数」を可視化 |
ENSOUヘルプデスクを使って、AI時代のナレッジマネジメントを実現してみませんか?
サービス資料をダウンロードする👇
導入相談をする(最短15分のオンライン相談)👇

