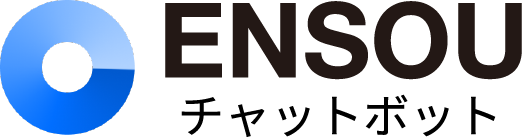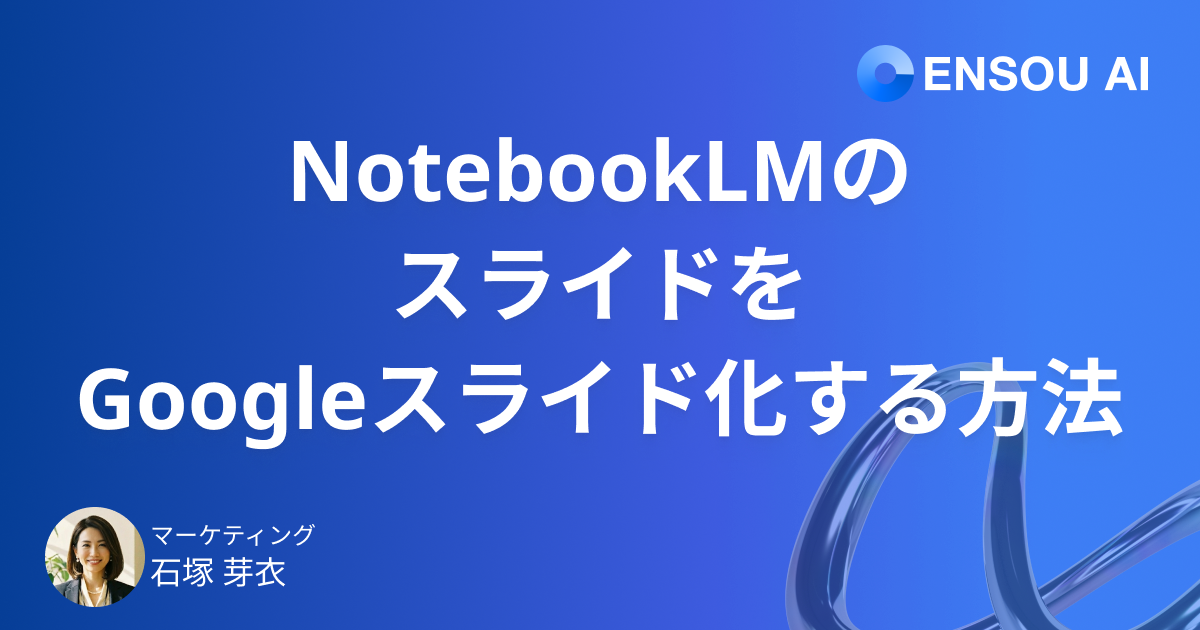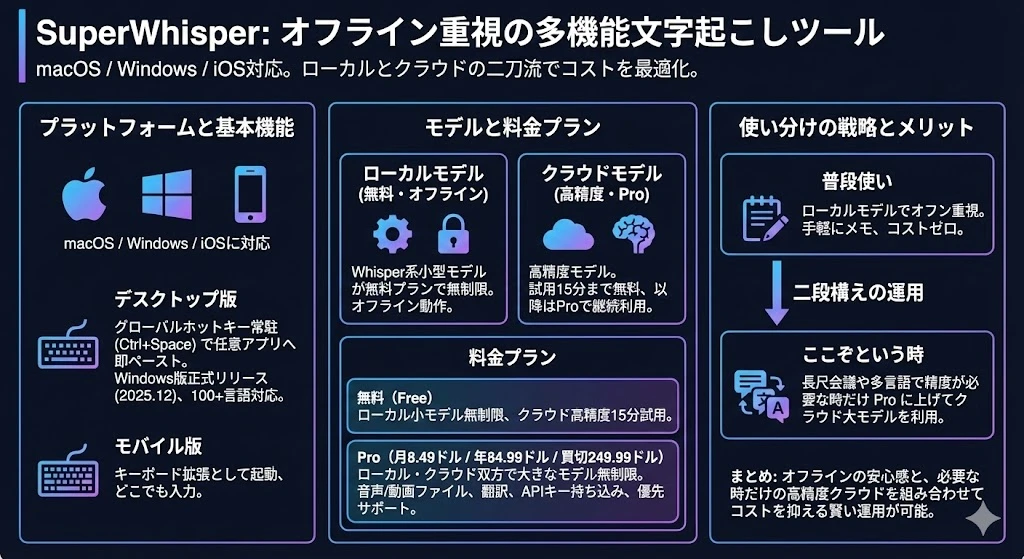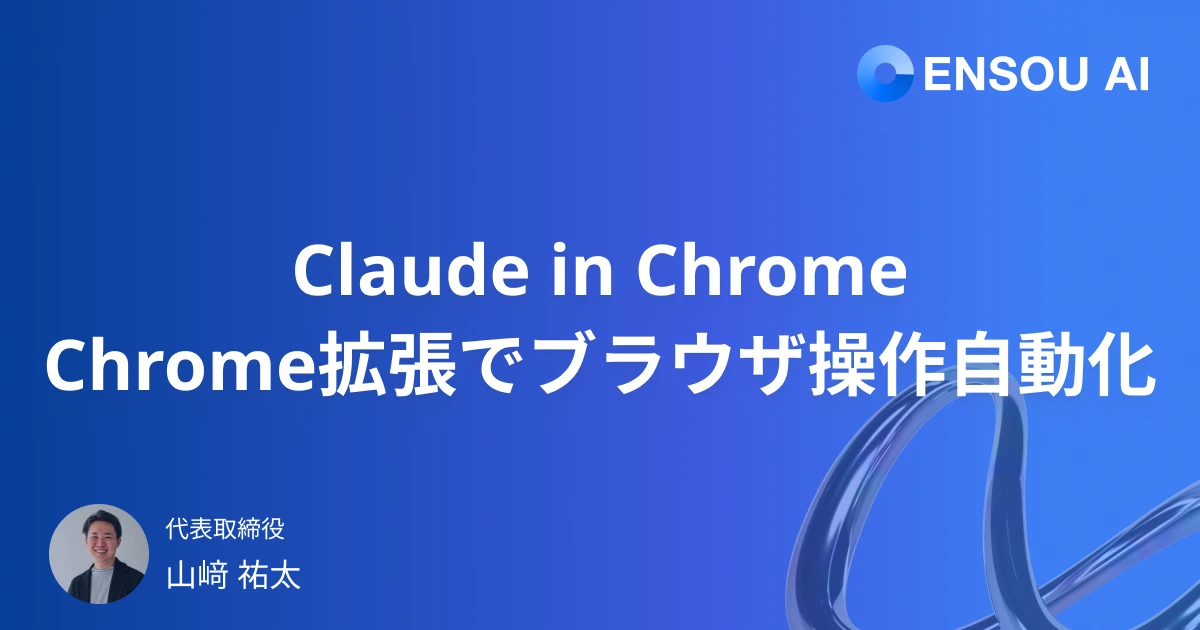2025年6月15日
FAQとチャットボット - 社内問い合わせ対応を効率化するためのツールを徹底比較
FAQとAIチャットボット、社内問い合わせ対応に最適なのは?ユーザー体験・運用コスト・改善性など4軸で徹底比較し、最適な選択を支援します。

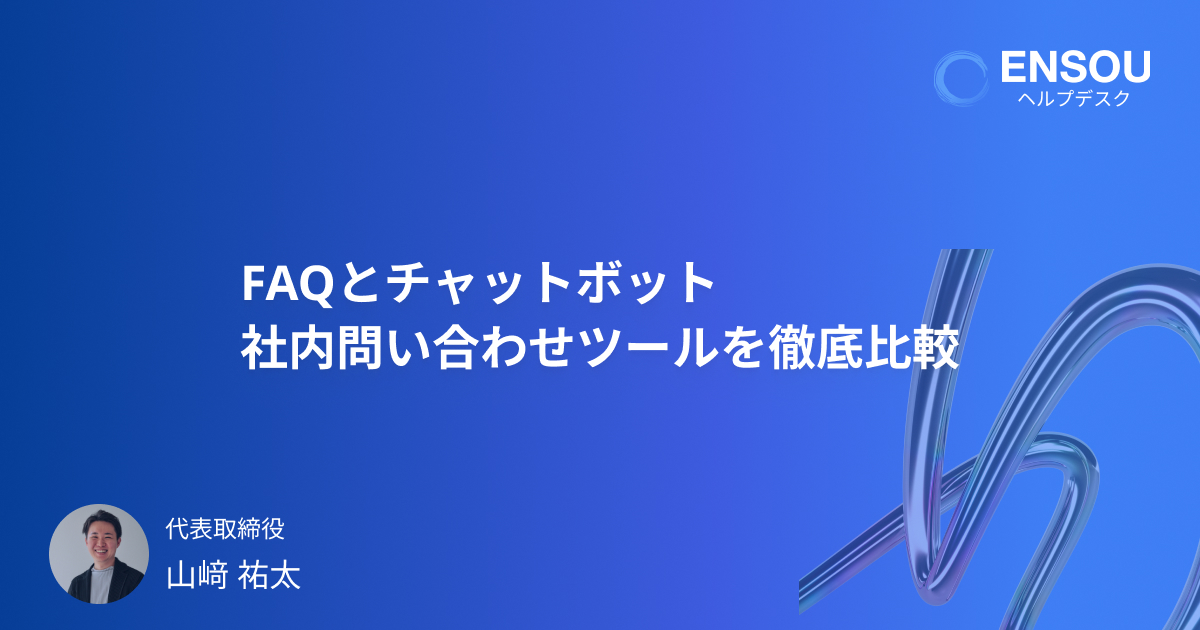
企業の成長に比例して、社内からの問い合わせは増え続けます。
また同じ質問が繰り返されることにうんざりしているバックオフィス系の担当者も多いのではないでしょうか。
社内ヘルプデスク業務を効率化するため、多くの企業が「FAQ」や「AIチャットボット」の導入を検討します。しかし、これらのツールのどちらを採用すればどのような成果が得られるのかについては、ツール毎の役割や効果が大きく異なるため、一概には判断が難しいのも事実です。
「結局、うちの会社にはどちらを使えば良いのだろうか」
「コストをかけて導入するので、絶対に失敗したくない」
この記事では、そんなお悩みを持つ情報システム部門、総務部門、そしてDX推進のご担当者様に向けて、FAQとチャットボットを4つの観点から徹底比較します。
それぞれのメリット・デメリットを明らかにし、貴社にとっての「最適解」を見つけるお手伝いをします。
社内問い合わせツールとしてのFAQとチャットボットの違い
まずはFAQとチャットボットがどんなものであるかを整理します。この違いを詳しく理解することで、自社にとっての最適なツール選定が可能となります。
FAQとは
FAQ(Frequently Asked Questions)とは、その名の通り「よくある質問とその回答」を一覧形式でまとめたものです。フォーマットとしてWebアプリケーションのものが主流ですが、ExcelやWordやPDFなどで作成・運用されているものも、FAQのひとつです。
ユーザーは、カテゴリを辿ったり、キーワード検索などで、自らの疑問に対する答えを探していくという操作を行います。
FAQは、ユーザーが自ら情報を探し出すプル型の情報提供を担います。またFAQ自体が網羅的に整備されていることが求められるため、社内業務に関する知識のデータベースとしての性質も有します。
チャットボットとは
チャットボットはユーザーが投げかけた質問の意図を汲み取り、必要な情報を参照しながら、最適な回答を提示するシステムです。
チャットボットには、シナリオ型(ルールベースとも呼ばれる)とAI型の2つの種類があります。
シナリオ型はあらかじめ定められたルールやシナリオに沿った定型の対応のみを担います。Webサイト上で「質問したいカテゴリを選んでください」 → 「ご用件は以下のうちどれでしょうか」など選択肢を選びながら回答を進める方式のチャットボットです。
AI型は大規模言語モデル(LLM)の技術を用いて、ユーザーが自由に投げかけた問いに対して、その意図を理解した上で、自身が持っている知識の中から最適な回答を都度生成するという方式のチャットボットです。
2025年時点では生成AI技術の進展によりAI型のチャットボットが主流となっています。特にシナリオ型のチャットボットは会話における全ての条件分岐を設定しなければならないため、継続的なメンテナンスが難しいという特徴があります。そのメンテナンスの手間をAI型のチャットボットが解決できるため、今後もこのシナリオが進んでいくことが予想されます。
本記事で扱うチャットボットは基本的にAI型のものを指します。
情報提供の方式はFAQのプル型と異なりプッシュ型であり、ユーザーが質問を投げるだけでチャットボットが必要な回答を返してくれます。
【徹底比較】社内問い合わせ効率化:FAQとAIチャットボットの違いとは?
さて、両者の基本的な違いが分かったところで、具体的な観点から2つのツールを比較していきます。
この後の比較におけるサマリーは下記の通りです。
比較観点 | FAQ | チャットボット |
|---|---|---|
ユーザー体験(UX) | △ユーザーの検索スキルに依存 | ◎ 会話だけで回答が得られる |
質問の対応範囲 | △ 定型的な質問のみ | ◎ 表記揺れや複数の質問に一括回答 |
運用コスト | △ 手動での更新が煩雑 | ○ 自動学習で負担を削減 |
データ分析と改善 | ○ 基本的な分析は可能 | ◎ ユーザーの真の質問まで分かる |
FAQ:△
FAQの最大の課題はユーザーが必要な情報に辿り着きにくいことです。
自身の疑問に対して事前に登録されたFAQの中から、合致するキーワードで適切に検索する、もしくは関連するカテゴリから手動で探す、といった手間が発生します。
その結果、「FAQは探しにくいので、直接電話やメールをしたほうが早い」となって、業務効率が低減してしまうのはよくあるパターンのひとつです。
チャットボット:◎
一方、チャットボットはユーザーが思っている疑問をそのまま入力するだけで、AIが質問の意図を理解して回答を提示してくれます。
検索キーワードを考えたり、カテゴリからたくさんの質問と回答のペアを探す必要がありません。それに加えて質問が不十分だったときは、チャットボット側から質問の深掘りをしてくれるため、より適切な解決策を得やすいことも特徴です。
FAQと異なり探す手間が少ないという点で、AIチャットボットを導入することは、社内の自己解決力の強化に繋がります。
質問の対応範囲
FAQとチャットボットでは回答できる質問の幅が異なります。
FAQサイト:△
FAQは基本的に一問一答形式のため、事前に想定・登録された質問のうちの1つにしか同時に回答できません。
ユーザーの質問は常に1つとは限らず、FAQに登録された質問と回答のペアの複数に跨るような質問もあり、その場合はFAQであればそれぞれのペアに辿り着く必要があり、情報を探す手間になります。
「新しいPCを購入するための申請手続きの方法と、新しいPC受領後の以前のPCの処分方法を教えてください。」のような質問であれば、「新規PC購入の申請方法」と「古いPCの処分方法」の2つの質問が含まれており、FAQで必ずしも一対一で対応するわけではありません。
チャットボット:○
RAGを用いたAIチャットボットであれば、複数の意図が含まれた質問であっても、一定適切に回答することが可能です。
いわゆるのLLMのレスポンスだけでも回答可能ですし、また意図の解釈と回答の妥当性を検証するプロセスが含まれた、推論(reasoning)モデルなどは、そういった対応を得意としています。
また、RAGであれば関連する文書を複数取得した上で回答を生成するため、FAQでいうところの適切なFAQを複数個取得して回答を生成するようなイメージになります。そのため、こういった複雑性のある質問への対応範囲などを加味すると、やはりAIチャットボットを活用するのが良い手であると考えられます。
管理者の運用・更新コスト
導入後のシステムのメンテナンスコストについて考えます。
FAQサイト:△
FAQサイトは、運用・更新の手間が非常に大きいという問題を抱えています。
新しい社内ツールが導入されたり、規定が変更されたりするたびに、担当者が手動で新しいQ&Aページを作成・追加し、古い情報を探し出して修正・削除しなければなりません。
コンテンツが増えるほどメンテナンス作業が複雑化し、管理が追いつかなくなる状態に陥りがちです。
また普段の業務に手一杯な状況を考えれば、FAQ自体をメンテナンスすることに時間をどれだけ割けるのか、という課題もあります。
チャットボット:○
RAGを用いたAIチャットボットは、運用負担を軽減する仕組みを備えています。
管理画面からQ&Aを簡単に追加できるのはもちろん、既存のマニュアル(Word, PDF, PowerPoint等)や社内規定、Webページなどを読み込ませるだけで、AIがその内容を自動で学習します。
これにより、FAQを手作業で一件一件登録する手間から解放され、業務の変更に伴って作成されたドキュメントを投入すれば良い、ということが言えます。
データ分析と改善のしやすさ
ツールを導入した後、問い合わせ対応数の削減に向けて、どのように改善サイクルを回していくかという観点です。
FAQ:○
多くのFAQのサービスであれば、各QAへのアクセス数、疑問が解決したか否か、といったデータを取得する機能があります。これによってどの質問がよく見られているのか、また解決されているまたはされていない質問の傾向を見ることで、改善をしていくことができます。
一方で、ユーザーの元々の疑問を知るための機能はないため、本来ユーザーが何に困っていたのかについては、別途アンケートや打ち合わせなどによってヒアリングの機会を設けて把握する必要があります。
チャットボット:◎
AIチャットボットはFAQサービスにあるようなアクセス数や疑問が解決したかを取得することができます。
またユーザーが自身の疑問をそのまま入力するため、どんな疑問についての対応を強化していくべきかがすぐに分かります。これは本来の疑問を入力するというチャットボットの性質だからこそ取得できる情報であり、チャットボットのFAQへの優位性と言えるでしょう。
現代の社内ヘルプデスクには「AIチャットボット」が最適解
ここまでの比較を踏まえれば、社内ヘルプデスクにはAIチャットボットの活用が不可欠であることがわかります。
もちろん、問い合わせの種類が10個程度しかなく、今後も増える見込みがない、といった極めて限定的な状況であれば、FAQで十分かもしれません。しかしそれ以上の問い合わせの種類に継続的に対応をしてくのであれば、AIチャットボットの活用を視野に入れるのが良いでしょう。
AIチャットボットを活用することにより、従業員の自己解決率を向上させ、問い合わせ対応やそれに関連する知識の属人化を防ぎ、管理者の負担を削減する、という理想的な社内ヘルプデスクを実現できます。
FAQが抱える「見つけられない」「答えられない」「更新が大変」「改善できない」という構造的な課題を、AIチャットボットはテクノロジーの力で解決します。